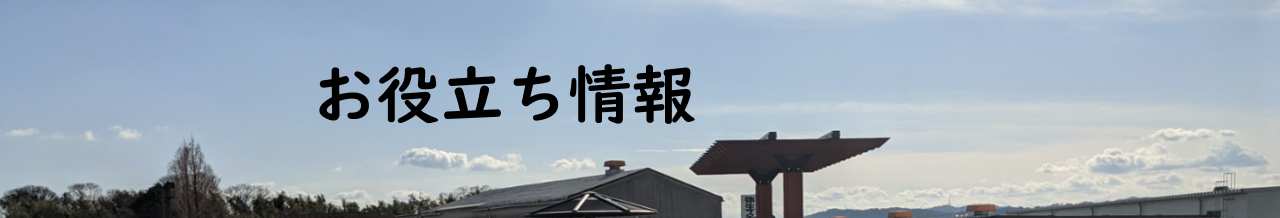夜道を自転車で走る際に安全確保は不可欠です。
ライト点灯はその第一歩でありますし、法律で義務付けられているのです。
特に女性や歩いている人にとっては、くらいところでの自転車が接近してくるのは怖いイメージがあります。
それに防犯の上からも重要である。また、夢占いにおいても夜道の自転車は意味深い象徴とされる。
自転車での夜道運転の危険性
夜道で自転車を運転するときは、
周囲の車や歩行者が自分の存在に気づきにくく、事故につながる恐れがあります。
特に、ライトがない場合は、自分を認識できない車や歩行者が多く、非常に危険です。
たとえば、昼間の運転だったけれど
自転車用ライトの必要性
自転車用ライトは、夜間に車や歩行者に自分の存在を認識させるために必要です。ライトがあることで、周囲の人が自分の存在を認識し、事故を防ぐことができます。
ライトの種類と選び方
自転車用ライトには、前方向に光を放つヘッドライトと、後方向に光を放つテールライトがあります。どちらも必要ですが、前方向に光を放つヘッドライトが特に重要です。また、明るさやバッテリーの持ちなど、機能や性能も重要なポイントです。
発電タイプ
- たいていは、自転車の前輪の右側に取り付けてあるダイナモを横に倒す形(旧式)で前輪に押し付ける。そうすると、前輪が廻ると同時にダイナモが回り始めて発電を行う。この場合は、ダイナモを回そうとする力が必要になるため、ペダルをこぐ時に少し重くなるため体力が少し余分に必要となる。
- 最近のもので発電式のライトであると、ダイナモが前輪のハブの中に組み込まれているものがある。これであれば旧式のものと比較するとペダルの重さはあまり負担にはなりません。
電池タイプ
- 自転車用として販売されているものは自転車に取付ることができるようになっているので自転車に固定できるので安心である。
- 懐中電灯をそのまま使うようにするには、ハンドルとか身体とかに取り付けることにしないと安全上問題が生じる可能性がある。
- 夜の仕事に使う頭に巻きつけるようにできるライトがある。釣りとかに利用されている。頭に取り付けることができるタイプだと両手が使えるの安全である。
- 電池タイプは、電池の持続時間に注意し把握しておく必要があります。自転車に乗っている途中で電池が切れることのないようにしておかなければなりません。乾電池を使用するのであれば予備の乾電池を用意しておくのもよいですね。充電式の場合は、照明時間内に帰宅するようにするか、交換できるライトを用意しておくとかすると良いと思います。
自動点灯タイプ
ライトの中にセンサーがあり、ライトが必要な暗さになると自動的に点灯してくれる。電池式のものならば、電池の残量に気をつけなければならない。
適切なライトの取り付け方
ライトを適切に取り付けることも重要です。ライトを取り付ける場所や角度によって、光の届く範囲や明るさが変わるため、取り付け方にも注意が必要です。
ライトの明るさ
法令では、10m先の障害物が確認できる明るさとして、300ルーメンが必要だとしてある。
300ルーメンだと解りにくいので、Wで表すと約30Wとなります。8畳の部屋にとりつける電灯が30W前後ですから結構な明るさになります。
ライトを点灯することで生じるメリット
ライトを点灯することで、周囲の車や歩行者に自分の存在を認識してもらえるだけでなく、自分自身も道路の状況をよく見ることができ、事故を防ぐことができます。
まとめ
自転車での夜道運転では、ライトの点灯がとても重要です。適切なライトを選び、正しく取り付けて、周囲の人に自分の存在を認識してもらい、安全に運転しましょう。
いかがでしたか。
自転車のライトの点灯は法令で全国どこでも適用されていますので注意が必要です。
自転車が好きな方で、明るい午後にツーリングにでかける。遠出をした場合は帰宅するころはどっぷりと日が暮れていることも有りえます。なので、必ずライトを点灯できるように準備をしていきましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。